皆さんこんにちは。昨晩夕飯を食べ過ぎて軽く体調が悪くなった私です。
節制という言葉を数日間は固く心に刻もうと思っています!!
さて今回のお話は子どもの勉強について。
5年近くもの間ほぼ毎日、娘に勉強を教えてきた経験を踏まえ、子どもに勉強のやる気を出させる方法について書こうと思っています。
毎日お子さんの勉強をみられている親御さんの何かの役に立てたらいいなと願いつつ。
もう何ならこの苦労を分かち合いたいです。
もう世の中のお母さんお父さんお疲れさまでございます!!
子どもに勉強のやる気を起こさせるには
さてこれから本題です。
子どもの勉強のやる気を出させるにはどうしたら良いでしょう!?ってことですね。
ここは本当に悩みどころです。
しかしながら私が5年近く娘と毎日数時間向かい合って教えてきた経験から、子どもを勉強に動かすのはこの6つの親の対応だなと実感しています。
- 子どもの勉強のやる気は結局は親の関わり次第
- 勉強しなさいと言うだけじゃダメ。実際に親が子どもの勉強を管理する
- 親が子どもの成績に意識を向ける
- 勉強をすることでどういうメリットがあるか、具体的に子どもに伝える
- 子どもに伝わるのは、親の言葉じゃなくて親の本気度だけ
- ほめる事、ねぎらう事、スキンシップは忘れずに
これについて以下に説明したいと思います。
子どものやる気は結局は親の関わり次第
最初から大きな結論を書いてしまいますが、
子どものやる気を引き出すのは、結局は親がどれだけ子どもの勉強に興味を持ち関わっているか
という所だと思います。
親が興味を持って真剣に子どもの勉強に関わってくると、子どもは自ずとその親の態度に引き込まれ、自然と勉強に意識が向き、それがやる気に繋がるものだと経験しました。
親が読書に興味があれば、子どもも興味を持つ
例えば私は読書が大好きなんですね。
そして娘にも読書が好きになって貰いたく、娘が生まれて生後6ヶ月~7歳まで毎晩絵本の読み聞かせ(1~4冊)を欠かさなかったのですが、そのおかげで娘は絵本、今では本が大好きな子どもに育ちました。今は2~3分の空き時間があればすかさずKindleを取り出し読書をしようとしています。
しかしこの子どもの本への興味は、親自身が興味があり、「子どもに本の読み聞かせをする」という事を通して、親自身の興味に子どもを巻き込んでいるからこそ生まれるのだろうと思います。
ちなみに以下は娘が幼稚園の時に何度も読み聞かせをした本達の一部です。
ナンセンスで楽しかったり(子どもはナンセンスが大好き!)子どもの目線で書かれている作品です。
親が熱心に教材を用意している姿を子どもは見ている
子どもの勉強の教材の用意も同様です。
親が興味を持って子どもの勉強について調べ、教材を用意して子どもに渡すと、子どもは多かれ少なかれ
「自分のために用意をしてくれた」
「自分を思って親が頑張ってくれた」
という気持ち持ちはじめます。
そしてそこから少しづつ、少しづつ
「勉強というものに興味を持ち始める」
流れになると体感ベースで思っています。
もちろん一日や一ヶ月というスパンでは、子どもは親の努力が分からないかもしれません。
しかし数年単位で考えると、「自分の態度は子どもに見られている」という実感が出てきますし、実際本当に子どもは親の態度を見ています。
子どもは親の興味のあるものに興味を惹かれやすく、そこからやる気に繋がると実感しています。
ちなみに私が色々と調べて落ち着いたのが隂山メソッドのドリルです。
勉強しなさいと言うだけじゃダメ。実際に親が子どもの勉強を管理する
さて、上記のように親が教材を用意して
「さああなたが自分の管理の下でしっかりやって下さいね。分からなかったら訊いてね。」
で、子どもは本当に熱心に勉強をやるでしょうか?
やらないですよね、実際。
絶対にだらける。
特に小学生のお子さんをお持ちの親御さんなら、私の意見に激しく共感して下さると思います。
勿論うちの娘も例に漏れずそうで、勉強にはまずやる気を出さない子でした。
私が一緒に勉強をしている間はまだしも、ちょっと目を話している隙にボーっとしていたり、絵なんか描いて遊んだりしています。
特に教え始めてから1~2年はもう毎回そんなんばっかり。今でもたまにあるくらいです。
これで何度私は娘とケンカになったでしょうか。
子どもが自分で勉強するという事への価値が見いだせるようになれば、子どもの勉強へのやる気はグンと上がりますが、それまでは絶対に親が時間管理・ペース配分管理をした方が良いです。グイグイと引っ張ってあげた方が良いです。
具体的には、親御さんがお子さんと一緒に勉強するのが一番です。
私も実際そうしています。
親が勉強している姿を見せると、子どもはどうあっても勉強せざるを得ないんですよね。
子どもが勉強する価値を見出し、それに伴って勉強へのやる気が出て来るまでは、親は一緒に勉強し、子どもの勉強も管理するとスムーズに行くかなと実感しています。
子どもの自主性の過度な尊重に専門家も警鐘
専門家も同じ立場を取っていました。

下記が引用です。
自由にさせたら、もっと勉強しなくなった・・・
残念ながら、これが現実です。
「楽しくやらなきゃ、頭に入りませんよ」は本当だけど、今勉強が成績不振でよくわからない、楽しくない子どもは永遠に楽しくはならないでしょう。
自己肯定感をもって取り組めるようになるまで、管理や手助けをしてやった方がいい
はっきりしているのは「できる」「わかる」「プライド」が続けば、子どもは勉強を自分でやりたい、もしくは、やるようになります。
親はその手前の「できる」「わかる」を実現できるように手助けしてやったらイイ。それが維持できれば「プライド」がでてきますから。
親が子どもの学校の成績に意識を向ける
これは一番最初のお話とかぶる内容かもしれませんが、親が興味を持って子どもの学校の成績に意識を向けることも大切だなと感じています。
とは言え学校の成績はどの親御さんでも興味があると思うので、特筆することでもないのかもしれませんが、とにかく
「親は自分の学校の成績が気になっているんだ」
「自分の学校の成績に期待しているんだ」
と思わせることが大切だと思います。
そして「あなたは頭が良い」という目で見てあげると、私の経験的に子どもはそれに応えようとし、それにともなって勉強への関心・やる気が出てきます。
勉強をすることでどういうメリットがあるか、具体的に子どもに伝える
子どもは具体的なメリットが分からないと、やりたくもないものは絶対にしない生き物です。
うちの娘も
「歯磨きが終わったら、前々から読みたかったあの本が読める!」
と言う状況では、ビックリするくらい早く、そして念入りに歯磨きが出来る子です。
このやる気満々な感じがお分かりでしょうか。
私は勉強を始めてからすぐに
「何故勉強することがあなたにとってメリットとなるのか」
という事を具体的に伝えてきました。
具体的に、という所がポイントです。
子どもは抽象的な話には一切理解を示しません。
具体的であれば何でも良いんです。下世話な話ですが
「勉強したら良いお給料が貰え、良いお給料を貰えるという事は、好きに出来るお金が増えることであり、好きに出来るお金が増えるという事は、欲しいモノが沢山買えるんだよ、ほらあの本とかこのオモチャとか。」
ここまで具体的に落とし込むと理解出来ます。
とは言え一回では無理ですし子どもは忘れますから、何度も言い聞かせることが大切です。
そうすることで少しづつ「親がなぜそこまで熱心に勉強をしなさいと口うるさく言うのか、なぜ勉強を一緒にやったりするのか」を子どもなりに理解しようとしはじめます。そこから勉強への関心・やる気が生まれてくるんですね。
子どもに伝わるのは、親の言葉じゃなくて親の本気度だけ
今まで色々と書きましたが、
忘れてはいけないのは「子どもは親の本気度を見ている」ということです。
もっと分かりやすく言うと、親の言葉じゃなくて態度を見ているんですね。
それが証拠に、子どもに優しく「集中して勉強してね」と言ったところで態度は全く改まらないのに、親が本気で怒って「集中しなさいって言ってるでしょう!!」というと、子どもはビシッと改まりますよね。
それは親の怒っている態度を真っ直ぐに見るからなんですね。言葉ではなくて。
「親が本気=これは守った方が良さそうだ」
となる訳なんですね。
ここで同意して下さった親御さん多いのではないでしょうか(笑)
ここが「子どもはずる賢い」「優しい大人にはなめてかかる」と言われるところですね。
だからこそ「子どもに勉強を教える時は親も本気であたる必要がある。そうしないと伝わらない」とこの5年間でがっちりと悟りました。
ほめる事、ねぎらう事、スキンシップは忘れずに
勉強の合間、勉強が終わった後にほめたり、努力を労ったり、スキンシップを取ることは本当に重要だなと感じています。
私も時として勉強を教えている時に厳しくなったりすることも多くありますが、最後に忘れずに子どもをほめたり労ったりするようにしています。
いくら自分のためだとは言え、子どもも一生懸命に勉強をして疲れているところ、「それくらい当たり前」みたいな態度を親にされたらやっぱり心も折れてしまうでしょうしね…。
反対に親からの温かい言葉一つで子どものやる気はかなり違ってきます。
実際いくら娘がプンプン怒っていたとしても、最後に私からねぎらいの言葉があると「やっぱり明日も頑張ろう」と思ってくれるようです。
まとめ
色々と書きましたが、子供の勉強へのやる気を引き出す方法について、ポイントをまとめました。
- 親が本気になって子どもの勉強に関わっていく
- 子どもの勉強を一緒にやる。時間管理なども親が担当する
- 何故勉強する必要があるのか何度も繰り返し具体的に伝える
- 教える時は本気で
- 勉強の途中や終わった後にねぎらいの言葉
何かのお役に立てたら幸いです。


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/185e4c42.03f34771.185e4c44.e27eaf72/?me_id=1213310&item_id=15921861&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3350%2F9784091053350.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3350%2F9784091053350.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/185e4c42.03f34771.185e4c44.e27eaf72/?me_id=1213310&item_id=18948257&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3831%2F9784091053831.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3831%2F9784091053831.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/185e4c42.03f34771.185e4c44.e27eaf72/?me_id=1213310&item_id=18948260&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3848%2F9784091053848.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3848%2F9784091053848.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
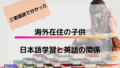
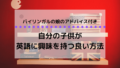
コメント