子どものやる気は算数の正解率に直結する
娘は日本なら小学校3年生であり、私も娘に小学校3年生の算数を教えています。
今のところ大きな問題はないのですが、1つだけ見過ごせない事があります。
それは娘のケアレスミス。
私自身も完璧に計算の出来た子どもではなかったのである程度目をつぶるつもりなのですが、娘のそれが私の数々の功績(!?)以上の偉業を成し遂げようとしているところ。
全く看過できない状況でございます!!
今までは「ちゃんとやりなさい」「やる気はあるの?」等と言っていましたし、実のところ今もお恥ずかしながらもそうなんですが(汗)
「これは親の方で何か働きかけないと、もしかして娘自身どうやってミスをなくしたら良いのか分からないのかも…」
という考えに至りました。
ケアレスミスは実力不足!?
「やる気はあるの?」というフレーズですが、私もそんな風に疑うことをしたくなく、あまり言いたくないフレーズなのですが、子どもはこうでも言いたくなるくらいあまりに気まぐれで、その娘のやる気の高低が、えげつないくらいに結果に明白に出てしまう生物です。
現に
- 娘がやる気100%(もしくは私に本気で怒られた直後)で問題に取り組む
…ドリルでもほぼ満点! - 私が優しい態度、そして不真面目な態度を優しく諭している間
…その正答率はだだ落ち!おーい!
ええ?なんですかこのちがい!?
私の教え方に問題ありなのかもしれませんし、そもそも私自身が教えるに相応しい人でないのかもしれません。他に家で頼める人が居ないから私が暫定的にやってる訳ですが、やるからには私も私なりの最善を尽くさないとなと思っている、それだけなんです。
と私の言い訳はここまでにして。
私個人的には陰山英男先生の方針を気に入っていて、よくこの方のサイト等をチェックしているのですが、そこにはこんな風に書かれていました。
「うっかりミスは実力不足」
こうもはっきり言われると
「もうその通りでございます」
と言うしかありません。
それならばケアレスミスを防ぐにはどうしたら良いかと考えて色々と調査をしてみました。
子どものケアレスミスをなくすために参考にしたサイト
そこで見つけたのはこんなサイトたちです。
参考サイトその1

このサイトによると、原因として
- 計算ミス
- 問題や答えの写し間違い
- 問題理解不足
だそうで、これを改善するためには
- 日頃丁寧に計算する
- 余白を綺麗に使う
- ケアレスミスをするたびに親から指摘する
と言う事のようです。
参考サイトその2

これによると
- 自分がミスするパターンを発見する
- ミスをしないようなルール作り
が大事なようです。
特に私が勉強になったのは1.の作業のパターンを見極める際の具体案で「うっかりノート」を作るというところ。ノートを取るのは確かに有効的かも!
参考サイトその3

これは原因について説明はなかったですが解決策として色んなことが挙げられていました。
- 問題文を2回読む
- 計算時、途中の式も丁寧に書く
- 字を丁寧に書く
- 解き終えたら見直しする
- 焦らない
算数の計算問題、早く解くのが良いのか、正確に解くのがいいのか
他にも色々と読み漁っていて全てをここに書くことが出来ませんが、計算力を上げるために
- 正確に解くのが大切なのか
- 早く解くのが大切なのか
どちらが大切なのかについても調べてみました。
結果としてはこれはあくまで子どもの計算のやり方によるようです。
日頃ゆっくり解く子には早さを求め、せっかちな子には正確に解くように。
お子さんの正確に合わせて声掛けを変えていくといいですね。
我が家の算数のケアレスミス防止策はコレ!
「問題で何を問われているのかを頻繁に見落とす」ケアレスミスへの対策
- 文章題は何に着眼して読むか、ポイントを伝える。
例えば娘は答える単位を勘違いして”kg”のところを”g”で答えたりするので、答えるべき単位をしっかり見るようにする。 - 計算問題は小さな声で囁く形で良いから音読する。それから計算に入る。
「計算間違い」ケアレスミスへの対策
- 字を丁寧に書かせる。子どもの書く数字は、数行に渡って無造作に書かれていたり、そうかと思うとその横の数字が1行の高さで収まっていたりで分かりにくいので、一律、罫線ノートの1行の中に収めるようにする。6と0を見分けられるように綺麗に書かせる。
- 途中の計算式を丁寧に書かせる。どう書いたら「丁寧に書く」という状態になるのか私が手本を見せ、その後子どもに書かせる。
- どこでそのミスが起こったのか子どもと一緒に検証する。ケアレスミスで間違った場合、ノートにその問題を書き写し、子どもと話し合いながら、その横に何をどう間違ったかを付け加える。
併せてこのパターンで間違えないようにするには、どうしたら良いか等の方法・アイデアを書く。
間違った計算問題の指摘は、どのように伝えるのが最善なのか
間違った問題について、どこで間違ってしまったのかの検証の際に、親が感情的にならないことが大切なんだそうですが…。
私としては、これに関しては、色んな意味で「子どもの性格によるのだろう」と言わざるを得ません。
例えば我が家の場合、その間違いを指摘すると、子どもはどのような言い方でも、まず素直には受け取ってくれませんし、子どもの聞く耳度は基本「話半分」以下になります。
なぜならうちの子どもは最高に負けず嫌い、自分のミスを認めたくないという気質があります。
もっと具体的に話しますと、私が以下の行動を取るとします。
そうすると子どもはこういう態度をとってきます。
- 娘の自尊心を損なわないように、優しく伝える…娘は「優しく言う→さほど重要度は高くない」という思考から「そこまで重要度の高くないものをなぜ言ってきて自分の気持ちを害するのか」という結果になり、
私の態度に更にタカをくくって「不機嫌になってもいい」「もう知りたくないから、取りあえず「ハイハイ」言えば相手は何も言わないしこの作戦で乗り切れ」という態度。
- 娘に体育教官のように厳しく伝える…最初反抗的な態度を示したのち、その手強さが予想を超えたものだと悟ってからは、今度は方向転換「親から厳しく言われる不憫な子」を演じだす。
おいどっちならあなたの心に素直に響くのか(泣)
こういう娘の態度を毎日目にしていると、いわゆる教育者が言っている内容は、全てが全ての子どもに当てはまるものではないなあと、心底思うのですよね。
うちの場合、自尊心を傷つけないように配慮して優しく言っていると、20回言ったところで娘の記憶にひとつも残っていません(経験済み)。
そんなわけで、この記事を読んでくださっている親御さんは、ご自身のお子さんの性格をよくご存知だと思うので、色んなあらゆるさじ加減で行くといいかなと思っています。


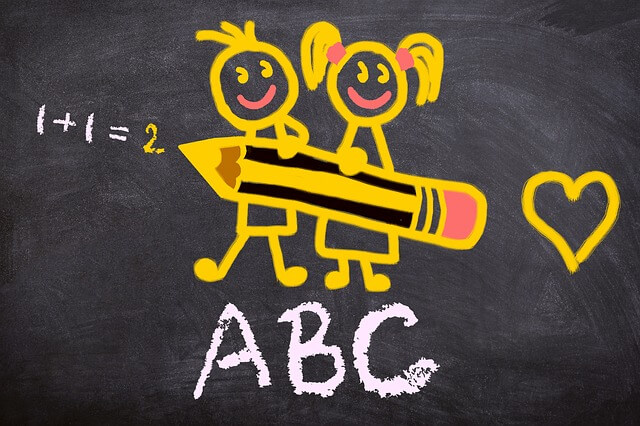

コメント